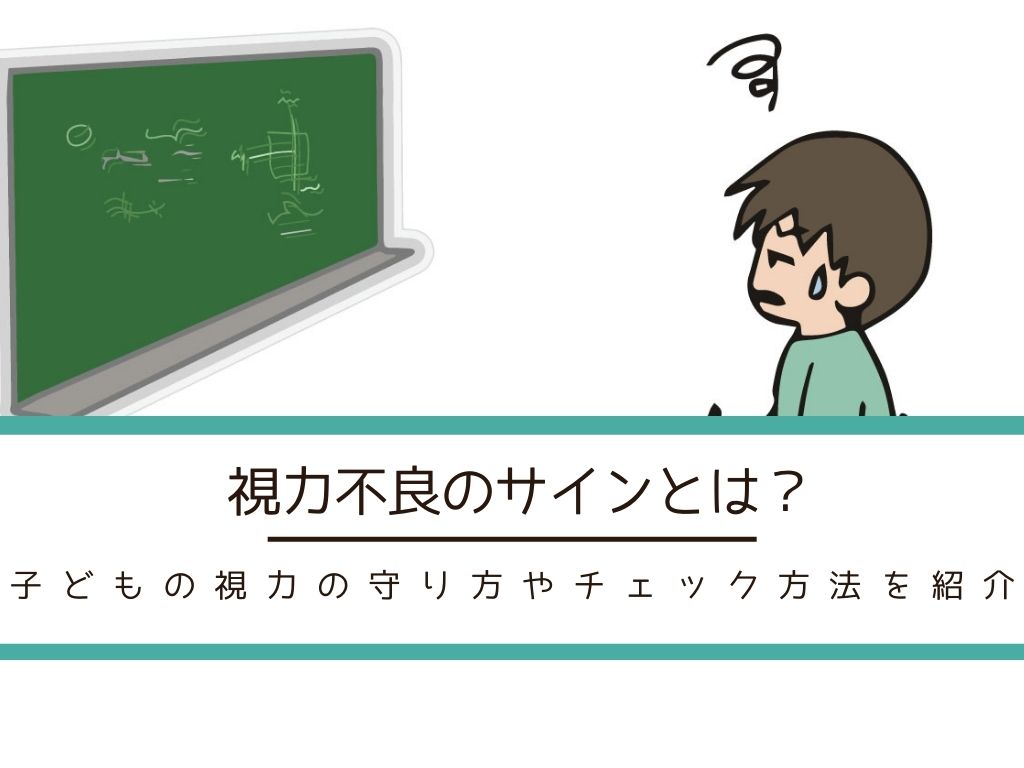
視力不良のサインとは?子どもの視力の守り方も
子どもの視力不良のサインってどんなものがあるのかご存じですか?
実は、子どもは自分自身で視力不良=見えにくさを自覚したり訴えたりすることはほとんどありません。
保護者や周りの大人が気づいてあげて、眼科検査を受けることがとても大切です。
視力不良のサインや子どもの見えにくさチェック方法についてくわしく紹介していきますので、「視力不良のサインってどんなものがあるの?」 と気になっている方にぜひ読んでもらいたい記事となっています。
視力不良を早期発見するためには、おうちでの様子を知る必要があります。
ぜひ最後までご覧ください。
この記事は、以下の内容について紹介していきます。
- 視力不良のサイン
- 子どもの視力の守り方
- おうちでできる視力不良チェック
それでは、視力不良が起こる病気やサインについて紹介していきます。
子どもの視力不良のサインとは?守り方についても
子どもが視力不良の場合、言葉で「見えづらい」と明確に伝えられる子ばかりではありません。
子どもにとってはいま見えている世界が全てであり、自身で気がつかないことがほとんどなのです。
もし自覚があったとしても、年齢や性格によりうまく伝えられない子もいます。 中には、「眼鏡をかけたくない」という気持ちから、視力不良を隠してしまう子もいるかもしれません。
サインは発しているものの、周囲が気づかないままでいると、「いつの間にか進行していた」なんてことも。
子どもが成長したときに、「あのとき早く気づけていれば」と後悔しても、あらゆることを経験して豊かに成長する時期は取り戻せません。
見えやすい環境で成長期を過ごすためには、見えにくさに早期に気がついてあげることが大事です。 そのためには、視力不良のサインについて、親がしっかりと理解しておきましょう。
視力不良の主な要因とサイン

子どもの視力不良について、どんなサインがあるのかを説明していきます。 子どもの見えにくさ(視力不良)の原因となり得るものはいくつもありますが、一般的に多い要因は下記のようなものがあげられます。
- 屈折異常(近視/遠視/乱視など)
- 眼の成長を阻害するもの(斜視/弱視)
これらの要因により見えにくさがある場合、子どもの様子(サイン)から推測されることがあります。下記に挙げますが、必ずあらわれるサインというわけでもないことに注意してください。
子どもの見えにくさ=視力不良のサイン
- 勉強するときに顔と机が極端に近い
- テレビを見るとき近すぎることがある
- 黒板の文字が見えないと言う
- 上目遣いになっている
- 眼を細めてモノを見る
- 顔を傾けて見ている
- 目をよくこする、まばたきが多い
- 読んだり書いたりする時間が苦手
斜視/弱視の場合のよくあるサイン
斜視や弱視が疑われる際は、上記のサインに加え、下記のような点が挙げられます。
- 目の動きが左右で違う
- 視線が合わない
- ボール遊びが苦手
- 階段を歩くとき極端に怖がる
- 片目を隠すと嫌がる
適切な治療により視力の回復が見込めるものもあるので、上記したサインを早期発見することが大切です。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
『アイケアークリップ』は、お子さんのメガネに付けるだけで、視力や姿勢の問題を解決できる優れたアイテム‼️姿勢の悪さや部屋の暗さを感知し、振動して警告してくれるので、正しい目の習慣が身に付きます👀✨
👇 いますぐ詳細をチェック 👇
-----------------------------
子どもの視力の守り方
近年、屈折異常のうち近視の子どもの増加/強度化が指摘されています。
詳しくは関連記事も参照ください。
近視はさまざまな要因(遺伝や環境)により発症/進行すると考えられていますので単純ではありませんが、日々の生活環境に注意することで近視の進行を少しでも抑制できるのではといわれています。
近視の進行を抑え子どもの視力を守っていくために、日常で気をつけたいことは以下の点です。
- 外遊びの推奨
- 正しい姿勢で勉強する
- テレビやスマホなど、画面に近づきすぎない
- ときどき目を休める
- 早期でこまめな眼科受診
- 屈折異常がある場合眼の状態にあった眼鏡をかける
外遊びの推奨

外に出て太陽光を浴びることで近視進行抑制になるといわれています。太陽光が近視抑制に関連する、眼軸長の伸びを抑える働きがあるとされており、世界中で研究が進められています。
2019年のHoらのシステミックレビュー、メタアナリシスでは学校教育に十分な屋外活動時間を確保することで4~14歳のアジア人の学童の近視発症が50%、近視進行が32.9%、眼軸長伸展が24,9%抑制できると記載されています。このような抑制効果は屋外活動時間の増加に応じて高まり、最も効果的な成果を得るために1日120時間以上の屋外活動をすることで、両親が近視の小児でも近視の発症率は下がり、片親が近視の小児とほぼ同じ割合になるとされているため、学校で屋外活動の時間を確保することが推奨されているとあります。
参考文献:Ho CL,Wu WF,Liou YM:Dose- response relationship of outdoor exposure and myopia indicators :A systematic review and meta-analysis of various research methods,Int J Environ Res Public Heals 16:2595,2019
中国の研究で1日20分の屋外活動を2回行うことでも近視の進行を有意に抑制されたとの報告もあるため、時間に縛られず、屋外活動に伴う熱中症や皮膚に対する負担なども考慮して行う必要があります。
外遊びはなかなか時間が取れない!などのお声もありますが、毎日意識してみてください。
正しい姿勢で勉強する

勉強するときは、机と顔が近づきすぎないように、姿勢良く座ることが望ましいです。・足をしっかりと床につける・背中は丸めずにあごを引く・イスと背中・お腹の間はこぶし1個分あけて座るなどといった基本的な姿勢を維持することで、適正距離が保てて近視が進みにくくなるでしょう。
テレビやスマホなど、画面に近づきすぎない

テレビ・スマホの画面と目の距離は、最低30cmは離すことが望ましいです。 至近距離での作業が続くと、眼軸長が伸び近視となる可能性が高くなります。 眼精疲労の原因ともなりますので、時間制限やルールを決めて使用することが良いでしょう。
スマホルールについて説明した記事もあります、ご参照ください。
ときどき目を休める
長時間勉強やゲームをしていると、目は休まる暇がなく、疲労を蓄積してしまいます。1回の使用時間を決めておき、適度に目への休息を与えることが望ましいです。
「20/20/20ルール」という眼精疲労防止ルールもありますよ。とてもかんたんな内容なので、日常にも取り入れやすいかと思います。
早期でこまめな眼科受診

子どもの様子が少しでもおかしいなと感じた場合は眼科を早期に受診しましょう。子どもの視力検査は難しく、精密な検査は眼科でしかできません。
最初は軽い近視の場合でも成長と共にあっという間にどんどん度数が進行して…という可能性もあります。 早めに受診し、その後もこまめに受診することが視力不良を悪化させないための近道です。
検査結果は問題なし!のとき

眼科を早期に受診する、本当は全ての子どもにお薦めしたいポイントです。
しかし日常の様子から「見えにくいかも」と感じて受診したのに、検査結果は問題なかった!というケースも珍しくありません。
このとき、保護者のなかには「心配して損した」「受診しなくて良かったのに」という声もあります。
ですがこれは誤解です。見えにくさが見逃されるよりも遥かに素晴らしいことですし、見えかたに問題がないのはたまたま今だけ、という事も多々あるからです。
子どもの見えかたは成長とともに変わります。
いまは良好でも来年はどうかな?と継続的に考えてください。
今回は、視力不良のサインと子どもの視力の守り方について紹介しました。
子どもは見えにくさがあっても自覚したり訴えたりすることはまれです。たとえ高校生でも自分で気が付かなかったというケースは多いのです。
子どもの視力を守るためには、目に良い健康習慣だけではなく、早期発見が鍵となってきます。 今回紹介した視力不良のサインをもとに、ぜひおうちで確認してみてください。
------------------------------
この記事を監修した人
松井萌珠さん

看護師・視能訓練士(広石眼科医院) / 北九州市出身 2008年看護師免許取得
病院勤務を経て医療法人広石眼科医院入職(現職)。眼科検査の重要性を痛感,勤務しながら九州保健福祉大学で学び2021年視能訓練士免許取得。小児眼科を辰巳貞子先生(小児眼科医)平良美津子先生(視能訓練士)に師事。眼科勤務に邁進しつつ、みるみるプロジェクトアンバサダーとして子どもの眼の啓発活動にも取り組む。



