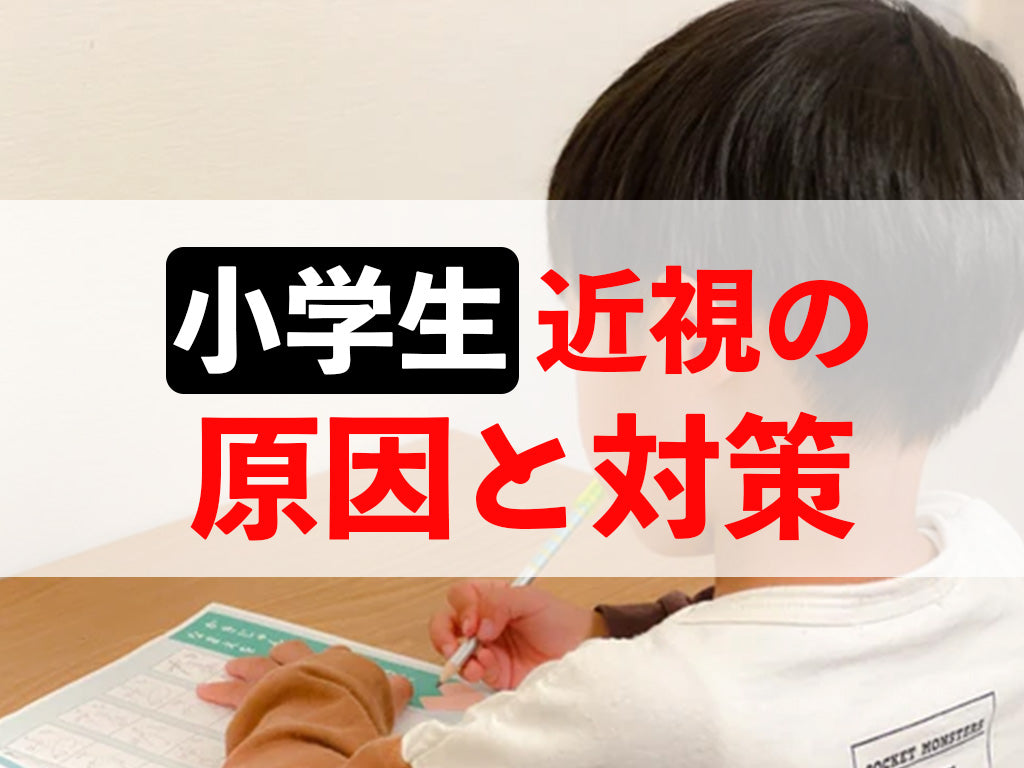
小学生の近視について|近視の原因は?近視は治る?
小学生の近視は、近年注目されている問題のひとつです。
近視の子どもが増えているのはなぜか、近視は治せるものなのかを解説していきます。
小学生の視力低下の割合

文部科学省の調査によると、2021年度の視力1.0未満の割合が小学生で36.87%、中学生で60.66%、高校生で70.81%という結果がでています。1)
小学生の視力1.0未満の割合を、1978年度と2021年度で比べてみましょう。1978年度は16%でしたが、2019年度になると36.87%になり、43年間で20.87%も増加しました。
この割合は、近視以外の遠視や乱視による視力不良も含まれますが近視の子どもは年々増加傾向にあります。
現代において小学生のうちから近視になるというのは決して珍しくないのです。
小学生の近視の原因

まず簡単に近視の原因について説明します。
近視が進行する原因は、遺伝要因と環境要因とがあり、両者が影響しあって発生する2)といわれています。
遺伝要因とは簡単にいうと、顔など身体的特徴が似るように、目の性質も両親に似ることがあります。日本弱視斜視学会によると、両親とも近視でない子どもに比べて、片親が近視の場合は2倍、両親が近視の場合には約5倍の確率で子どもも近視になりやすいと言われています。3)
2)所敬.屈折異常とその矯正.改正第5版,金原出版,2009,145
では次に環境要因について、詳しく解説していきます。
スマートフォンなどの普及

近視が増加している環境要因のひとつに、スマートフォンなどのデジタル機器の普及があります。
ゲームや動画配信アプリ等、小学生でもスマホやタブレットを使用する時間が長くなっているのが現状です。
近視は、近くを長時間見続けることで、進行します。
外遊びの減少

子どもの外遊びが減ってしまったことも、近視の原因のひとつだといわれています。
子どもが1日に外遊びをする時間は1981年は2時間11分、2001年は1時間47分、2006年は1時間12分と年々減少傾向にあります。
ゲームなどの家庭内で遊べるものが普及したこともありますが、都市化が進んで子どもの遊べる場所が減少してしまったことや、塾や習い事をする子どもの増加も原因として考えられます。
外遊びで太陽光を浴びることによって、近視の予防や、近視の進行を抑制できるという研究結果が出ています。
近視の原因に外遊びは関係無いように思われるかもしれませんが、子どもの視力にとって外遊びは非常に重要です。
---------------------------------
『アイケアークリップ』は、お子さんのメガネに付けるだけで、視力や姿勢の問題を解決できる優れたアイテム‼️ 姿勢の悪さや部屋の暗さを感知し、振動して警告してくれるので、正しい目の習慣が身に付きます👀✨ 👇 いますぐ詳細をチェック 👇
------------------------------------
近視は治るのか?
近視は一度発生すると治すことは難しいです。
遺伝が原因にもあるように、近視自体は病気ではないからです。
また、近視は身体の成長や生活環境で進行していくものなので、あくまで予防と進行の抑制が重要です。
近視の治療法は?

さきほど近視の治療は難しいと書きましたが、ある条件の近視に限り、見え方の改善や近視を抑制する方法があります。
1.オルソケラトロジー
程度の軽い近視には、オルソケラトロジーという視力矯正方法があります。
オルソケラトロジーとは、就寝中に特殊なコンタクトレンズを装着し、睡眠中に角膜の形状を矯正し、日中の視力を回復させる治療方法です。
継続して使用することによって、近視の抑制に効果を生みます。
大人と比べて角膜がやわらかい子どもは、オルソケラトロジーの効果が出やすいとされています。
2.仮性近視への点眼治療
真の近視ではなく一過性に近視のように見える状態になることがあります。3)
環境要因により一時的に目のピント調整をし過ぎてしまい、見え方が不安定になることを仮性近視(偽近視)といいます。仮性近視が疑われる場合は、目薬を使い、目のピント調整をする筋肉を休ませるという治療方法があります。
小学生の近視対策

近視を治すことは難しいので、近視にならないようにする「予防」と、近視になった場合は「進行を抑制する」ことが重要になってきます。予防と進行抑制の対策をいくつか挙げていきます。
正しい姿勢を意識する
正しい姿勢で勉強や読書をすることが、近視対策において重要です。背筋を伸ばして、目と対象物の距離を30センチ程度離しましょう。
寝転んだままの読書やテレビを見ることも、目にとってよくありません。悪い姿勢をとることで、近視が進むことはもちろん、左右の視力に差が出てきやすくなってしまいます。
子どもの場合、無意識に姿勢が悪くなってしまうことがあるので、両親や周囲の大人が教えてあげることが大切です。
スマートフォンなどは時間を決めて使用する
近視の原因のひとつである、近くを見る時間を減らす必要があるので、スマートフォンやタブレット等のデジタル端末は使用時間を決めておくとよいでしょう。また、就寝前にスマートフォンを使用すると、ブルーライトの影響で眠れなくなってしまう可能性があります。
明るい場所で作業する
勉強や読書は明るい場所で行うと近視対策に効果的です。一般的に勉強や読書をする際には300ルクス必要だといわれています。これはワットで表すと15ワットから20ワットに相当します。
暗いところでの作業は、見えづらさから目を酷使してしまうので、15ワットから20ワットを目安に、明るい場所で作業するようにしましょう。
まとめ

小学生の近視は、予防をすることと進行の抑制が重要です。
日々のデジタル端末の使用方法等で、近視が発生しても進行を遅らせるように対策していきましょう。
【実際の臨床現場では】

テレビやネットニュースなどで頻繁に取り上げられている小学生の近視ですが、実際に眼科領域の研究においても近年最も注目されている分野の一つになっています。
世界中で子どもの近視が増加しているいま、眼科医/視能訓練士は日々アップデートされる医療情報に注目しながら、最新の知見を取り入れ検査や診療にあたっています。
この記事を監修した人
岸川亜洲香(きしかわあすか)視能訓練士

熊本県出身 福岡国際医療福祉学院(現:福岡国際医療福祉大学)卒業
卒後、福岡市立こども病院眼科に入職。尊敬する視能訓練士平良さんから小児眼科を学ぶ。その後眼科クリニックにて小児眼科の経験を積み、出産を機に退職。母親として子育てと仕事を両立し、患者さんや親御さんに寄り添える視能訓練士を目指す。


