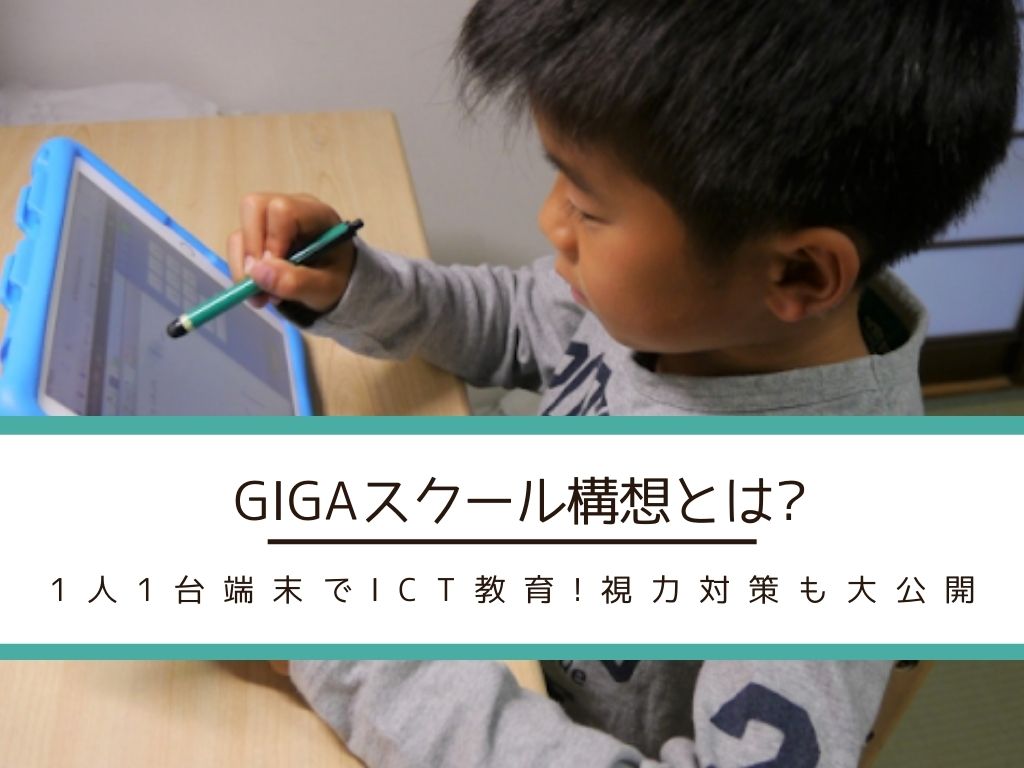
GIGAスクール構想とは?1人1台端末でICT教育!視力対策
はじめに
文部科学省の発表によると 「GIGAスクールにおける学びの充実」に4億円の予算をかける見込みです。(引用:令和3年度文部科学関係予算のポイント )
しかし
- 莫大な予算をかけるGIGAスクール構想とは?
- 1人1台端末で子どもの成績は上がるのか?
- ICT教育普及に伴う視力への影響は?
と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
今回は下記を解説します。
- GIGAスクール構想とは何か
- ICT教育で得られる利点と注意点
- 1人1台端末の未来へ対抗する視力対策
本記事を読めばGIGAスクール構想とは何か理解を進め、デジタル過多な子どもの視力対策の参考になれば幸いです。
GIGAスクール構想とは

画像引用: 令和2年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果(概要)(令和3年3月1日現在)
GIGAスクール構想とは2019年に文部科学省から発表された、児童に1人1台端末を配り授業を進めること(ICT教育)です。
GIGAはGlobal and Innovation Gateway for All(全員に国際舞台と革新的な扉を)の略、 ICTはInformation and Communication Technology(情報通信技術)の略。
ICT教育はインターネットのような通信技術を 授業で使うことを指します。
GIGAスクール構想とは、予想外に早く進んだ施策です。
2024年を目安に導入予定でしたが、コロナが猛威を振るい前倒しになっています。
文部科学省の調べによると、 令和3年3月時点で児童1.4人につき1台パソコンを保持できるようになりました。
GIGAスクール構想推進の取り組み

GIGAスクール構想とは何かお伝えしましたが、具体的には次のような取り組みが進められています。
- 生徒1人1台端末の配布
- 教師1人1台端末(パソコンかタブレット)常備
- 各教室に大型モニター設置
- 無線LANの整備
- 統合型校務支援システムの導入 生徒の出欠や健康状態、成績・指導内容をクラウド上で管理
- ICT支援員の配置 機械が苦手な先生のためのサポート員で、業務や能力を規定した目安もあり。
ICT教育にて学校側で必要な施策3つ
ICT教育が広まりつつある中、学校内で何をするべきか3つお伝えします。
指導者の強化
1つ目に先生もICT学習が必要です。
教材作成や生徒の評価、校務、授業等で通信技術を上手く活用する必要があるからです。
ICTにおける生徒の質問に答え指導できるように、勉強も重要でしょう。
情報セキュリティ対策
2つ目に情報セキュリティに関する知識がなければ、思わぬところでデータが世に出る可能性もあります。
スパムメールや悪質なサイトに入りウイルスで管理中の情報が見れなくなる、個人情報流出の恐れ等もあるため対策が必要です。
GIGAスクール構想とは、先生や生徒の情報セキュリティの知識とシステムの整備が重要になる分野でしょう。
自宅での使用ルール作成
家で端末利用する場合のルール作りが大切です。
例えばコロナの影響でオンライン授業に切り替わると、先生は直接監視できないからです。
家庭で使用する場合目安がなければ、無限に端末を使用する可能性があります。
自宅での使用ルール作成は必須でしょう。
『アイケアークリップ』は、お子さんのメガネに付けるだけで、視力や姿勢の問題を解決できる優れたアイテム‼️姿勢の悪さや部屋の暗さを感知し、振動して警告してくれるので、正しい目の習慣が身に付きます👀✨
👇 いますぐ詳細をチェック 👇
ICT教育のメリット3つ
1人1台端末教育の利点を3つお伝えします。
教員の作業が簡略化
1つ目に端末により、指導者の労力が減る点です。
例えばテストはタブレット上の回答や正誤が瞬時に先生の端末に共有され、採点の手間が省けるでしょう。
結果もデータ管理されるため、生徒一人一人の苦手分野がわかり指導点が明確です。
情報の共有や統合で、仕事は楽になり質も上がるでしょう。
質の高い教育を受けられる
2つ目に小学生からプログラミングを学ぶ等、高品質の教育を受けることができます。
基礎問題が完璧な子は応用問題に取り組み、苦手な子は繰り返し学習する等、 個別学習も可能です。
マット運動で自身の姿を撮影し、改善点を分析する等、動と静を融合させた取り組みを行っている学校もあります。
実際に1人1台端末が導入された小学校の児童によると「タブレットは紙と違いごまかしがきかないため、頭に入りやすい」、「映像込みで先生の話が理解しやすくなった」等の声もありました。
子どもの発言力を高める
3つ目に発言が苦手な子も発表しやすくなります。
1人1台端末が実現すればチャット機能を使い、簡単に自分の意見を発信できるからです。
今までの授業スタイルは、決まった生徒が発言する傾向は否めませんでした。
しかしICT教育が進めば、ほぼ同時に様々な生徒の発言がタブレット上に出されるため意見交換もしやすくなるでしょう。
ICT教育のデメリット3つ
反対に1人1台端末の教育が進むと、待っている危険性を3つお伝えします。
機械トラブル
1つ目は使用パソコンやタブレット等に不具合が起きる場合がある点です。
端末が映らないトラブルが発生すると授業が停止します。
機械が苦手な先生は対応に苦慮するかもしれません。
ICT活用で余計に仕事が遅くなる可能性もあります。
端末に依存
2つ目に端末に頼りすぎるかもしれません。
実際「体育でタブレットに注力し、運動があまりできていない」と懸念する1人1台端末導入校の先生もいました。
字を書く機会の減少で、上手く表現できない子が出る可能性もあります。
アメリカの研究で学生に同じ動画を見せ、一部は紙とペン、残りはパソコンで内容をメモしてもらったところ、前者の方が覚えが良かったそうです。
端末は生徒の興味を引きますが、 依存しすぎは様々な弊害を生むかもしれません。
視力低下
3つ目に視力が落ちる可能性があります。
デジタル機器に触れる機会が、物理的に多くなるからです。
下記等が原因で、視力の低下も懸念されています。
※近視の進行による裸眼視力の低下
- 良くない姿勢→読み書きでも同じことが言えますが、良い姿勢の保持は子どもたちの成長にとても大切です。デジタルデバイス画面はついつい普段以上に近づいて見ようとしてしまい、姿勢が崩れやすいもの。この「近すぎる」距離が近視進行の一因といわれています。
- 画面と目が近すぎる→近くを見ることは、遠くを見ることよりも調節が働き眼に負担がかかります。近視の進行と生活環境の関連は深くその中でも近業(近くを見る作業)が近視進行の環境因子として大きく、近業時間が長いほど近視化すると言われています。近業距離が33㎝未満だと近視の程度が強くなると研究結果として報告されています(参考文献:Gong Y Zhang X,Tian D et al:Parental myopia, near work, hours of sleep and myopia in Chinese children. Health 6:2014)
ICT教育の推進で、子どもたちの良好な裸眼視力維持が困難になる可能性はあります。
1人1台端末時代を乗り越える視力対策

https://aiglasses.tokyo/products/holdon-ai-glasses
ICT教育が普及すると子どもが勉強の誘惑となるYouTubeの見方を簡単に覚え、ご心配かもしれません。
学校のルールで使用制限がある場合も先生の目は家庭まで行き届かず、あなたが子どもの端末視聴時間を管理しうんざりしているかもしれませんね。
でも、「そろそろ見るのをやめなさい」と都度注意するのは今日で終わりにしませんか。
子どもの自己セーブが理想ですが、教育は大変と思ったあなたはメガネのAi/Glasses(エーアイグラス)がおすすめです。
10秒間隔で設定できるアプリと連動し、規定 時間を超えると振動で教えてくれます。
端末との距離もセンサーで測る優れもの。
子どもの自己管理力を育み、視力低下の要因となる長時間のデジタル機器視聴を抑える商品情報はこちらからどうぞ。
まとめ
- GIGAスクール構想とは、1人1台端末等情報通信技術を活用し授業を進めること
- ICT教育のメリットは、先生の負担軽減と質の高い教育推進、生徒の発言力向上
- デメリットは端末機器不具合と依存度が高まる可能性、裸眼視力の低下
- ICT教育の発展で子どもの視力が心配なあなたはAi/Glasses(エーアイグラス) がおすすめ
ICT教育が進みデジタル機器を見る機会はどうしても増えてしまうかもしれません。
しかし上手くアイテムも利用しながら、子どもの視力対策を行い勉強に専念できる環境を整えていきましょう。
眼科スタッフの一人として
わたしが勤務するクリニックに来院されるお子さんたちに聞くと、やはりタブレット使用の授業が急増しているようです。
パソコンの操作や機能に詳しくなり、最新の情報、世の中の流れに適応できるようになるなど、良い点はたくさんあると思います。
しかし、それに伴う眼に関わる問題も増えていくと思われます。
GIGAスクール構想に伴うデジタルデバイスの普及と眼の問題について眼科スタッフは作業環境をしっかりとヒアリングし、眼科医に伝える必要があると思います。
保護者の方ともお子さんの作業環境について改善できること(無理のないルールを一緒に考えたり、作業距離や20‐20‐20ルールなどこういう方法もあるよ等のアドバイス等)お子さんの視機能の発達に寄り添った医療を提供できるよう、私たち眼科医療従事者も知識のアップデート、アプローチが大切だと考えています。
-----------------------------
この記事を監修した人
松井萌珠さん

看護師・視能訓練士(広石眼科医院) / 北九州市出身 2008年看護師免許取得
病院勤務を経て医療法人広石眼科医院入職(現職)。眼科検査の重要性を痛感,勤務しながら九州保健福祉大学で学び2021年視能訓練士免許取得。小児眼科を辰巳貞子先生(小児眼科医)平良美津子先生(視能訓練士)に師事。眼科勤務に邁進しつつ、みるみるプロジェクトアンバサダーとして子どもの眼の啓発活動にも取り組む。



