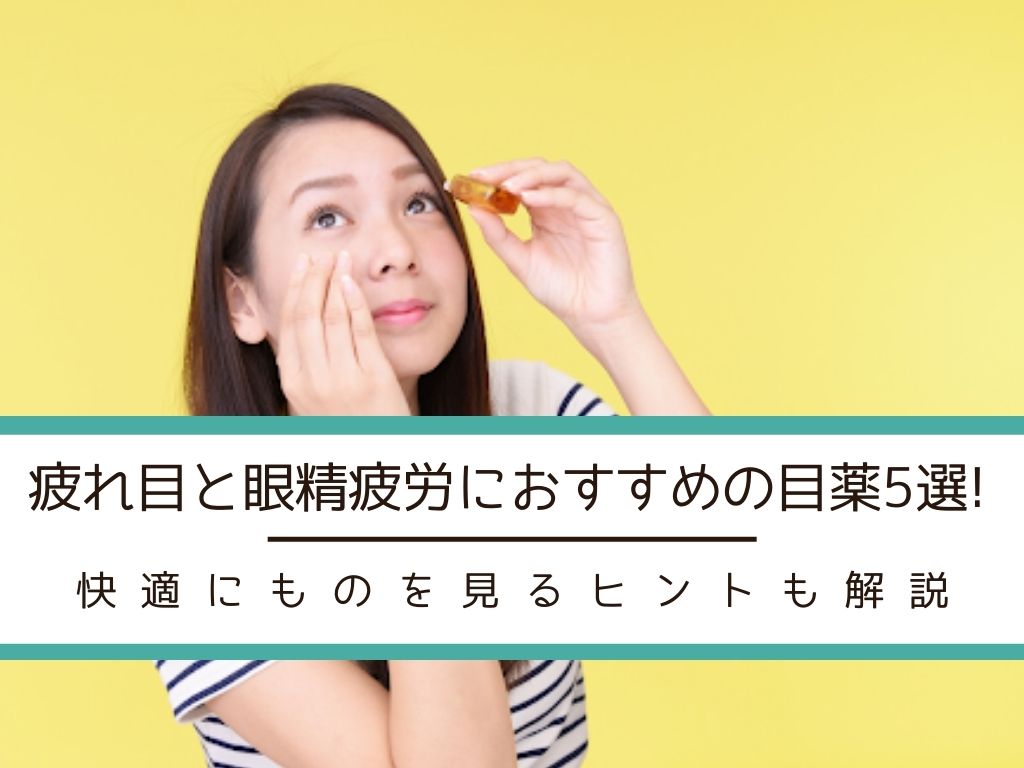
疲れ目、眼精疲労は目薬で改善するの?
はじめに
デジタルデバイスが身近にある現代、多くの人が感じているであろう目の疲れ。
疲れ目を感じたときの手軽なアイテムとして目薬を使用することもあると思います。この記事では疲れ目に対する目薬の上手な使い方について解説します。
疲れ目と眼精疲労の症状
まず、疲れ目と眼精疲労の違いについて簡単に説明します。
一般的に疲れ目の症状には、目が重たいなどの不快感や目の痛みなどがあります。
眼精疲労とは目の症状に加えて頭痛や肩こりなどの全身症状が出現し、休息や睡眠をとっても十分に回復しえない状態をいいます。
所敬、他.現代の眼科学.改訂第11版,金原出版,2012,374,52参考
このように疲れ目と眼精疲労については分けて考える必要があり、今回は目の症状の改善について考えていきます。
疲れ目に目薬は効くの?
現代問題となっている疲れ目の多くが、パソコンやスマホなどのデジタル機器や本など、近くを長時間見ることによって起こります。
デジタル機器の画面を見るとまばたきの回数が減るため、ドライアイになることも多く、疲れ目とドライアイは密接に関係しています。
疲れ目の症状を目薬で治す…というのは難しいですが、目の不快感を軽減するために目薬で目に潤いを与える、という使い方が良いと思います。
目薬を差すときの注意点3選
目薬入手後の注意点を3つご案内します。
使用期限を守る
1つめに、開封後は基本1ヶ月以内に使い切りましょう。ただし開けてから10日以内推奨の目薬もあるため、各目薬に記載された期限厳守が重要です。
なぜなら開封すると、食品のように品質が落ちていくからです。
開封して時間が経過すると雑菌が繁殖する恐れもあるので、使用期限を守りましょう。
点し方に気をつける
目薬を点す前は手を洗い、目薬の蓋の口は上向きに置きましょう。
雑菌が入らないよう、点し口がまぶたやまつ毛に当たらないよう注意が必要です。
目薬を点した後はまばたきをせず、10秒から20秒目をつむって待ちます。目頭に涙を排出する穴があるので、目頭あたりを軽く指で押さえると、目薬の液を目に留まらせることができ、更に効果的です。ティッシュで抑えすぎると液体を吸い取るため、目の周りの溢れすぎたものだけ拭き取りましょう。
あくまでも目に潤いを与えることを目的とする
前述したように、目薬だけで疲れ目の改善を求めることはできません。
目薬を点して気持ちが良い、目が楽になるという方は続けて問題ないですが、症状の改善を望む場合は眼科を受診することも重要です。
--------------------------------
『アイケアークリップ』は、お子さんのメガネに付けるだけで、視力や姿勢の問題を解決できる優れたアイテム‼️姿勢の悪さや部屋の暗さを感知し、振動して警告してくれるので、正しい目の習慣が身に付きます👀✨
👇 いますぐ詳細をチェック 👇
--------------------------------
疲れ目:目薬以外の対処法
疲れ目の症状を軽減する対処法をお伝えします。
1.目を休める
原因となるパソコンやスマホを見る時間が長くならないように、こまめに休憩をとるようにしましょう。画面から目を逸らし、遠くのものを見ると、効果的に目を休ませることができます。睡眠をしっかりとることも大事です。
2.目を温める
目元を温めることで血行が良くなり、目の痛みや疲れを和らげることが可能です。市販の温かいアイマスクや蒸しタオルを使用すると良いでしょう。
3.眼鏡やコンタクトレンズの度数調整
見えづらい場合や過剰な矯正は目の疲れにつながります。
そのため、定期的に度数をチェックし、自分の見たい距離に合った適切な度数の眼鏡を使用しましょう。
まとめ
残念ながら目薬だけで疲れ目を改善することは難しいです。
デジタル機器の付き合い方を見直し、目をいたわりながら、目薬は上手に活用しましょう。
【実際の臨床現場では】

疲れ目を自覚していらっしゃる方は本当に多いですね。
残念ながらそのうち、きちんと眼科受診される方の割合は低いのではと実感しています。何年も悩んでいて、市販の目薬を何本も点しているのに改善しない…いよいよ困って眼科受診…というケースが目立っています。
疲れ目や眼精疲労は、ドライアイ/見るものとの距離/眼位とよばれる眼の位置など実は原因がさまざま。自己判断と全く違う思いもよらない原因が見つかることも多々あります。
疲れ目で悩まれている方は、自己判断で対策せず、眼科受診されることを心からお勧めします。
---------------------------
このサイトでは、お子さんの姿勢や目と見ている物の距離を正しく保つグッズをご紹介しています。
以下の画像リンクから、ぜひごらんください。↓
この記事を監修した人
岸川亜洲香(きしかわあすか)視能訓練士

熊本県出身 福岡国際医療福祉学院(現:福岡国際医療福祉大学)卒業
卒後、福岡市立こども病院眼科に入職。尊敬する視能訓練士平良さんから小児眼科を学ぶ。その後眼科クリニックにて小児眼科の経験を積み、出産を機に退職。母親として子育てと仕事を両立し、患者さんや親御さんに寄り添える視能訓練士を目指す。



